
望海風斗主演 舞台『マスタークラス』オフィシャルレポートが到着!
2025年3月14日(金)東京・世田谷パブリックシアターにて、舞台『マスタークラス』が開幕。
この度、本作のオフィシャルレポートと舞台写真が到着しました。
「今日はこれまで」
決してキメ台詞ではなく、さりとて軽すぎずもしないそのひと言を残して、望海風斗が、いや、マリア・カラスが背を見せて退場していった時、張りつめていた集中力がふっと切れて軽いめまいのようなものに襲われた。後から思うと失礼にも映ったのではないかと不安なのだが、スタンディングオベーションが続く客席で容易に立ち上がれなかった。ただ凄いものを観た、そんな感覚にいまも囚われている。望海風斗を主演に擁して日本で約30年ぶりに上演された『マスタークラス』は、それほどに切れ味鋭い舞台であり、極上の芸術論だった。
20世紀最大のプリマドンナとして、世界中のオペラファンを虜にしたマリア・カラス。クラシック音楽やオペラに関心の薄い人でも、名前だけは聞いたことがある、と思わせる域にまで達した稀代のディーヴァが、オペラ歌手引退後ニューヨークのジュリアード音楽院で若き歌手たちに実際に行った「マスタークラス(公開授業)」を題材に、芸術に身を捧げ、愛を求めた彼女の人生を浮かび上がらせたのが、マリア・カラスの熱心な信奉者だったテレンス・マクナリーの手による戯曲からなる、この『マスタークラス』だ。作品は1995年に世界初演。翌年、海外戯曲の上演に力を注いでいた黒柳徹子主演で早くも日本初演が実現している。今回はそこから約30年ぶりとなる上演で、卓越した演出力で快進撃を続けている森新太郎演出、望海主演による新たな舞台、新たな公開授業が展開されている。
鏡とパネルが市松模様に配された背景の前に、下手寄りにグランドピアノが1台。上手側に簡素なテーブルと椅子。というシンプルな美術の中、伴奏者がピアノの前に座る。やがてマリア・カラス、つまり主演の望海が上手奥から背筋を美しく伸ばし、足音も小気味よく颯爽と登場してくると、極自然に拍手が沸きおこる。だが
「拍手はやめて」
とカラスは客席を制する。今日の主役は自分ではなく、これはリサイタルでもない。あくまでも公開授業なのだ、と説かれたその瞬間から、劇場に集った観客はマリア・カラスのマスタークラスを聴講している生徒に変貌する。そんなカラスは椅子が高すぎるから足台が欲しい、クッションも、それに客席が明るすぎるし、ここは熱すぎる……と様々なセクションに幾多の要求をし続ける。かと思うとふいに「あなた良い人ね、私の言うことにいちいちうなづいてくれて」などと、突然聴講生である客席の一人に語り掛けてくるという巧みな滑り出しで、劇場中を作品世界に引き込んでいく。
そこで繰り広げられるのはカラスが、そして劇作家のマクナリーが心に持っていた人生を捧げるに値する至高の芸術に対する献身が詰まった授業だ。1幕でソプラノの生徒1人、2幕でソプラノとテナーの生徒1人ずつにカラスが行うレッスンは、一見辛辣なようでいて、芸術に向き合う術を伝えようとする情熱にあふれている。音楽大学のいくつかが学生の減少に苦しんでいると伝え聞く令和の感覚とは、かなり異なるだろうことをあらかじめ前置きしたうえで、昭和の音楽教育のなかにいた身からすれば、世界が認めたディーヴァであるカラスが、惜しみなく自分の経験を教えようとする姿勢にはむしろ驚かされるほどだ。確かに言葉の端々はかなり辛辣ではあるが、ユーモアもあり、作品背景を全く理解していない生徒に対して、これでは教えることがないと一度は追い返そうとするものの、結局は渾身のレッスンを施し、芸術という客観的な点数化が難しい世界で、頂点に達することの困難さを説き、その選ばれし一握りの存在になるための果てしない道程を指し示そうとしていく姿は崇高でさえある。
その想いの根底には、この世界にオペラがなかったとしてもちゃんと明日はくるが、芸術のある世界が全くない世界に比べてどれほど豊かなものか、という、文字通り身を削って美を追求し、役に生きようとしたカラスの人生から劇作家マクナリーが読み取り、本人の想いも投影した、人間にとっての「芸術」の大切さを訴える信念がある。これは2020年、突然世界を覆った新型ウィルスの脅威のなかで、声高に叫ばれた芸術不要論に対する、まるでアンサーとも取れる戯曲だ。だからこそ、この作品を四半世紀前に既に書いていたマクナリー自身が、新型ウィルス罹患によって世を去ったのは痛恨の極みだが、宝塚歌劇団トップスターとしての集大成を控えた只中で、舞台が止まるという二度と起きて欲しくない経験をした望海と、劇場の灯が完全に消えた世界を見てきた森が、芸術の大切さを説くこの作品をいま世に送り出していることに、感動せずにはいられない。
実際、この『マスタークラス』のマリア・カラス役を演じる俳優の負担は、並大抵のものではなく、上演には大きな勇気がいったことと思う。何故ならこの戯曲は「緊張するのは準備不足だから。自信がないから」「音楽をよく聴いて言葉の意味を考えて。全て書かれているから」「芸術に近道はありません。楽な道もなし。それが日常と違うところ」「芸術っていうのは、支配することです。この瞬間には、この歌い方しかないんだって、お客さんに思わせることです」等々、紡がれる言葉、台詞のひと言一言が気高い芸術論だからだ。それだけに、演じる側にこれらの言葉たちに見合う説得力がなければ、作品の意図するところが伝わらない恐れが大きい。
例えば「舞台に魔法でパッと現れるなんていうことはないんです。必ず、始めに登場があって、最後には退場がある。登場と退場の間に芸術があるんです」と教え、役として登場してみてと生徒に言ったあと、それがとても納得できるものではないと思った時、自分がやってみましょう、とカラス自身が実践する。ここで彼女の言葉が体現されていなければ、作品はもう成り立たない。これは考えるだに恐ろしいことだ。だが、その高い壁を望海は、あぁそういうことかと納得させる登場で見事に乗り越えていく。その芝居力には感嘆させられるし、作品のなかで役としてはほぼ歌わないにもかかわらず、カラス本人の歌唱録音や、生徒の歌声に合わせて、意図するところを伝えようとする場面では、音楽が身体に入っている人ならではの親和性を見せ、あたかも歌ったかのように感じさせてくれる。更にカラスが人生の全てを捧げた芸術を捨ててもいいとさえ焦がれ、愛した20世紀最大の海運王オナシスとの会話を一人芝居で演じる場面では、ある意味お手のもののはずの男役芸とは明らかに異なる非常にミニマムな表現で、鮮やかに二人を演じ分けていくなど、難度の高い戯曲を制した、俳優としての望海自身の着実な進化が素晴らしい。生身の俳優が撮り直しの効かない舞台で、目の前で戯曲を体現する興奮がここにはある。
その作品世界をまるごと引き受けた演出の森の、時に見えることよりも雄弁な暗闇や、市松模様の背景に映し出される映像など、様々なセクションとの共同作業による創出も見事で、終盤に向けて引き絞られていく舞台の緩急が際立った。
また共演者では、ソプラノ1(ソフィー)の池松日佳瑠が「見栄えが悪い」と断じられてしまう役柄に、持ち前の愛らしさを封印したヘアメイクや表情で果敢に挑み、緊張感からのパニックを巧みに表現。ソプラノ2(シャロン)の林真悠美はマスタークラスには場違いのドレスアップでの登場から、歌うことと演じることを分けて考えているシャロンの勘違いとプライドの高さを色濃く見せて、終幕につなげる大任を果たしている。テナー(トニー)の有本康人はカリカチュアの効いた動きを大仰に見せつつ、カラスと共鳴していく美声を披露。道具係役の石井雅登はピントの外れた緩慢な動きが、緊張感の続く舞台をホッとさせてくれる貴重な存在になり、トニ―のカバーも務める実力者ぶりが光る。そして、作品の音楽監督と共に伴奏者(マニー)役も務める谷本喜基が、出過ぎず引き過ぎずの流麗なピアノ演奏で舞台を支えただけでなく、終幕カラスに対して全くリアクションなく退場する素っ気なさが、カラスの孤高を象徴して強い印象を残した。
他にソプラノ1と2のカバーを務める岡田美優、道具係のカバーとプロンプターの中田翔真も大きく紹介している制作の姿勢が、芸術の大切さを訴える作品に相応しい。総じて歌うこと、役になりきるために集中することを求めるカラス同様、聴講生である観客の集中も求められる舞台の、劇場中を包むピーンと張った空気感から、こよなき芸術への敬意と愛を感じる。一人でも多くの人にこの作品を体感し、芸術の、演劇のある世界の幸福を噛みしめて欲しい。そうストレートに思える出色の舞台だった。
(取材・文/橘涼香)
公演概要
舞台『マスタークラス』
■公演日程
3月14日(金)~23日(日)東京・世田谷パブリックシアター
3月29日(土)~30日(日)長野・まつもと市民芸術館 主ホール
4月5日(土)~6日(日)愛知・穂の国とよはしPLAT主ホール
4月12日(土)~20日(日)大阪・サンケイホールブリーゼ
■キャスト
マリア・カラス 望海風斗
ソプラノ1 池松日佳瑠
ソプラノ2 林真悠美
テナー 有本康人
道具係 石井雅登
伴奏者 谷本喜基
スウィング 岡田美優、中田翔真
■スタッフ
作 テレンス・マクナリー/演出 森 新太郎/美術 伊藤雅子/照明 佐藤 啓/
⾳響 けんのき敦/衣裳 西原梨恵/ヘアメイク 西川直子/演出助手 須藤黄英/
映像 松澤延拓/技術監督 今野健一/舞台監督 佐々木智史、山矢源
制作 ⼤迫彩美、桑原涼⼤
プロデューサー 貝塚憲太/スーパーバイザー 穂坂知恵子
エグゼクティブププロデューサー 渡辺ミキ
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。















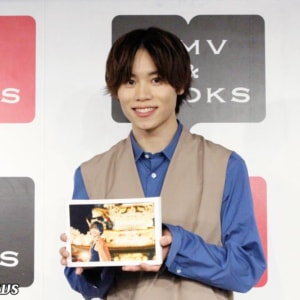






この記事へのコメントはありません。